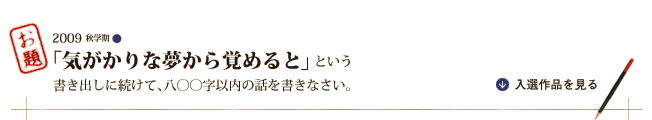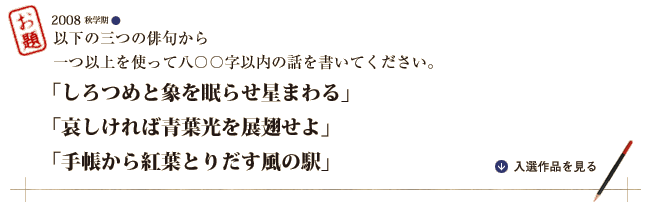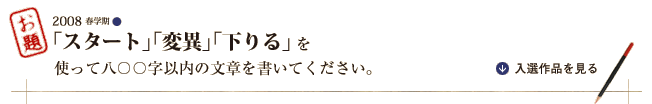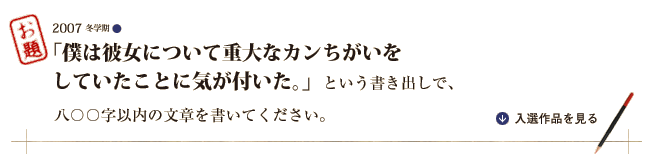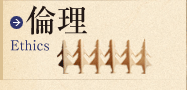【入選】 Kさん「エンドレスライフ」 【講評】 短い字数の中で書き出しを活かして小説の構造を組み立てたのが素晴らしい。
力みのない書きぶりで完成度の高い作品になった。【全文紹介】 「エンドレスライフ」
気がかりな夢から覚めるといつもの日常が待っていた。いつも同じ時間に鳴る目覚まし時計、いつも着るスーツ、いつも読む新聞、いつも通る道、いつもと同じ風景。いつもの日常と何等変わりは無かった。一つだけ気になる事といえば、あんなに気がかりだった夢の内容を忘れてしまった事だ。何か自分にとって重要な事だったはずなのに……何も思い出せない。しかし、こんな事をいつまでも考えている暇は無い。なんといっても今日、二月二十九日は俺の将来が決まると豪語してもいい大事なプレゼンテーションがある日なんだから。そして俺は半分緊張し、半分期待に胸を膨らませながらいつもの道を急いだ。いつもと同じ時間に会社に着き、いつも座る席につき、プレゼンテーションの準備をした。
プレゼンテーションの結果は自分でも完璧と思う程の出来栄えだった。実際、会社の上役達にも絶賛される程だった。このプレゼンテーションを成功させた事は俺の薔薇色の未来に一歩足を近付けたという事だ。こんなめでたい日にはやはり一杯してから帰るのが一番だろう。そんな事を考えながら俺は帰宅の用意をして、いつもと同じ時間に会社を出た。いつもと同じ風景のはずなのに全てが特別で光り輝いているように見えた。その頃には俺は朝気がかりな夢を見た事も忘れていた。内容を覚えていない事も。しばらく歩くと俺のお気に入りの店が見えてきた。後は横断歩道を渡るだけ
「キキーッ」
「ドンッ」
自分の身に何が起きたのか分からなかったが、自分の体が一瞬浮いた事だけは分かった。
「ピリリリリリ」
目覚まし時計の音で目が覚めるとそこは俺の部屋だった。とても気がかりな夢を見た気がするが……何も思い出せない。そういえば今日は二月二十九日。俺の将来が決まると豪語してもいいプレゼンテーションがある日だ。早く会社に行く用意をしないと。そして俺はいつも通りに用意をして家を後にした。
【審査員特別賞】 Hさん 【講評】 読後感がさわやかで、高校生らしい実感のこもった作品である。 【全文紹介】 手帳から紅葉とりだす風の駅
この言葉で思い出した中学時代の自分。季節は秋、僕は好きな女の子がいた。好きになると、目で追ってしまう、けど直接話せなくなるタイプ。目で追うだけの日々が続いた。
でもある日、チャンスが来た。六人くらいで地元で遊ぶことになった。僕はメールでしか彼女と話したこともないのに、と思ったが当然行った。
ゲーセンやカラオケ、いろいろ楽しく遊んだけど、僕はやはり見てるだけであった。しかし、このチャンスを逃したら、もう一生無理だと思い、がんばった。カラオケで気持ちを込めて歌ったバラード、彼女には届いていたのだろうか。ゲーセンでとったぬいぐるみ、あげるべきだったかな。
そんなくだらないことを考えながら、時間だけが過ぎていった。夕方になって、帰る時間が迫ってきた。果たして今日中に告白できるのだろうか、タイミングがつかめないまま不安になるばかり。でもその時は来ると信じ、最後に公園にたどり着いた。みんなで今日のことを振り返りながら話していた。すると、
「おれ飲み物買ってくるわ」と言ったら、
「あたしも行くよ」
まさかの言葉に驚きを隠せなかった。思わず、「え、いいの?」って聞いてしまった。周りに笑われた。結局近くのコンビニまで二人で行った。歩きながら、
「紅葉きれいだね」
「秋だね」よくわからない会話が続きながらドキドキしていた。帰り道にきれいな茶色の紅葉を見つけた。
「わーすごいきれい!」
もうここしかないと思い、
「よかったらおれと付き合って下さい!」
と言って紅葉を渡した。
二年後、あの時の手帳を開いたら紅葉が出てきた。
「あの時は見事にフラれたなぁ」
【入選】 Nさん「ヒキコモリ」 【講評】 「スタート」「下りる」の使い方にはもう一工夫あってもいいが、「変異」をキーワードに自己と世界の関係を緊張感をもって描けている。今後さらに洗練していってほしい。 【全文紹介】 ヒキコモリ
人として生をうけた「私」、「人生」をスタートさせた「自分」。最初は順調だった。しっかりと地に足をつけ、人として生きていた。
「私」が成長していくにつれ、それはおきた。変わりゆく人に町に「自分」に、変異する世界に対応できなくなった。毎年変わる流行の服や髪を身につけ、三ヶ月ごとに変わるドラマを見て、毎月発売される雑誌を読まなければ「私」は「私」として生きられなかった。そんな「私」を「自分」は憎んでしまった。そんな「私」に「自分」は嫌気がさした。だから「自分」は「私」をとじこめた。二階の自室にとじこめた。
「自分」は「私」を、「私」が変わらないと生きていけない世界から切り離した。それは「私」、「社会を生きる自分」の死と同じ意味だった。「私」は変異していなければ生きられなかったからだ。「私」が変異するためには、変異する世界に生きていなくてはならないが、今「私」がいる部屋はいくら時がたとうが変異しなかった。やがて「私」は死んだ。
部屋には「自分」しか生きていなかった。「自分」は変異しない世界でしか生きられなかった。「私」が死んだ今、「自分」は部屋にいることしかできなかった。扉を開け、階段を下りて、外に出る、たったこれだけのことができなくなってしまった。
部屋の中で死んでいるような生活。生きているようで死んでる「自分」。「自分」は「人生」を歩んでいるといえるだろうか、それはきっと「私」だけが知っている。
【受賞作】 Sさん「彼女」 【講評】 作品に荒さは残るものの、読む人を圧倒する勢いがある。
作者の今後の伸びに期待したい【全文紹介】 「彼女」
僕は彼女について重大なカンちがいをしていたことに気が付いた。彼女は僕にこんなにも大きなことを隠していたのか。僕は押さえ切れない怒りと悔しさを抱え、彼女を連れて病院の玄関のドアを蹴破り、走り出した。目的地は川である。
彼女と初めて出会ったのは昨年の夏祭りのことだった。それは運命的な出会い。目があった瞬間から僕らは愛しあっていた。僕には彼女しかいないと確信したし、彼女も僕だけを必要としていた。すぐに一緒に暮らすことになった。彼女との生活は全てが楽しかった。僕の作った食事を彼女がおいしそうに食べる姿を見るだけで幸せになり、時々きらきらしたキレイな瞳で見つめられると天にも昇る思いだった。彼女は少々乱暴な性格をしていて、ある日リボンを買ってあげたら、気に入らなかったのか怒ってかみちぎってしまった。そんな彼女でさえこの世にあるどんなものよりも大事に思えた。そんなだから、初めて手をつないだ時、僕の手は緊張の汗でぐっしょりぬれていた。でも、彼女の手も湿っていて、それがまた恥ずかしくてずっと幸せに感じた。昨晩は勇気を出して、結婚を申し込んだ。無口な彼女は無言で首を縦にふってくれた。
彼女の様子がおかしくなったのは今朝のことである。起きたら彼女が苦しそうな声を出してうずくまっていた。僕はあわてて、彼女の軽い体を抱き上げ病院に走った。必死だった。彼女にもしものことがあったら僕は死んでしまう。
診断の結果は食べ過ぎによる腹痛であった。明日からは有頂天になって食事を作り過ぎないようにしよう。ほっと胸をなでおろしたのもつかの間。続く医師の言葉に僕の全てがひっくり返った。彼女は僕の恋人になり得ない存在であった。男だったのである。彼女、いや、彼は僕をだましていたのだ。これで、彼がやけに無口だったのにもかわいいリボンに対して怒ったのにも説明がつく。彼は半年もの間タダ飯を食い続け、毎日僕に掃除をさせていたのだ。だまされる僕もなんて愚かだったのであろう。
だから、僕は今彼を連れて川へ向かっているのである。彼を僕の家から追い出すために。二度と亀なんて飼うものか。